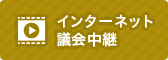政務活動費
最終更新日:令和7年7月30日
政務活動費の概要
1 政務活動費とは
地方議会は、首長と並ぶ二元代表制の一翼を担う機関として設置され、地方自治体としての意思を決定する役割や執行機関の監視機能を果たす役割などを担っており、議員は、市民の代表として、議案の審議・審査や政策の立案などの様々な議会活動を通じて市民の負託に応えるため、的確に状況を把握し、地域の実情に応じた政策が実現されるよう、自らの役割を果たさなければなりません。
また、近年では、地方議会の持つ政策立案機能の発揮が期待されており、地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっています。
これら地方議会の活動を活発化するためには、日常的に広範な調査研究活動が必要不可欠であることから、その基盤を充実させるため、地方自治法において、政務活動費(旧政務調査費)が制度化されました。
政務活動費は、地方自治法及び各地方自治体の条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、会派又は議員に対し交付されます。
京都市では、地方自治法及び京都市政務活動費の交付等に関する条例(以下「条例」といいます。)に基づき、会派及び議員に対し、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「調査研究活動等」といいます。)に要する経費の一部として交付されます。
具体的には、調査研究、研修、広報広聴、要請・陳情、会議の開催・会議への参加、資料作成、資料購入、通信運搬、備品消耗品の購入、補助職員の雇用、事務所の運営に必要な経費を対象としています。
2 政務活動費制度の沿革
| 政務調査費の制度化 (平成12年5月) |
地方議会議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにより、地方議会の審議能力を強化するため、平成12年5月に地方自治法の一部が改正(平成13年4月1日施行)され、「政務調査費」が制度化されました。 |
| 政務活動費への制度変更 (平成24年8月) |
政務調査費制度を見直し、幅広い議員活動又は会派活動に充てることができるよう、平成24年8月に地方自治法の一部が改正(平成25年3月1日施行)され、「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を各自治体の条例で定めることとされました。 |
3 京都市会における政務活動費制度の沿革とこれまでの取組
| 政務調査費の制度化 |
「京都市政務調査費の交付に関する条例」を制定 | |
| 領収書等の公開に関する取組 |
1件5万円以上(事務所費・人件費を除く)の支出に係る領収書等を収支報告書に添付し、一般の閲覧に供する取組を開始 | |
| 領収書等の公開に関する取組 (平成20年度交付分から適用) |
全ての支出に係る領収書等を収支報告書に添付し、一般の閲覧に供する取組を開始 | |
| 指針の策定 (平成20年4月1日施行) |
「政務活動費の運用に関する基本指針」(以下「指針」といいます。)を策定し、政務調査費の具体的な支出の考え方や按分の基準などを明確化(平成20年度交付分から適用) | |
| 政務活動費への制度変更等に伴う条例改正 (平成25年3月1日施行) |
地方自治法改正を受け、「京都市政務調査費の交付に関する条例」を「京都市政務活動費の交付に関する条例」に改正 【改正内容】 ・ 名称を「政務調査費」から「政務活動費」へ変更 ・ 政務活動費を充てることができる範囲を規定 ・ 収支報告書等をインターネットなどで公開する等、政務活動 |
|
| 領収書等のインターネット 公開 (平成28年8月31日開始) |
閲覧に供している全ての書類のインターネット公開を開始(平成27年度(5~3月)交付分から実施) | |
| 使途の透明性の向上等に 関する要綱及び指針の改正 (平成29年4月1日施行) |
使途の透明性の向上等を図るため、「京都市政務活動費取扱要綱」(以下「要綱」といいます。)及び「指針」を改正(詳細な説明はこちらを、改正後の「要綱」及び「指針」は「11 関連規定」を御覧ください。)
|
|
| 人件費に係る支出に関する 要綱及び指針の改正 (令和3年度交付分又は令和4年度交付分から適用) |
(令和3年度交付分からの見直し) ・ ・ (令和4年度交付分からの見直し) ・ |
|
4 交付対象、交付月額及び交付時期
| 交付対象 | 会派及び議員 | |
| 交付月額 | 会派14万円(会派に所属する議員1人につき1月当たり) 議員40万円(1月当たり) |
|
| 交付時期 | 四半期ごとに交付(4月、7月、10月、1月) 年度末において残額があった場合は返還されます。 |
|
5 政務活動費を充てることができる範囲(使途基準等)
政務活動費の支出に当たっては、使途の透明性の確保に努めなければなりません。京都市会では、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めるとともに、具体的な運用に関する基本原則、按分等の基準、支出が認められない経費等を定めた「指針」を策定しています。
6 京都市会における支出の考え方
(1)主な支出例
| 調査研究費 | 資料印刷費、委託調査費、文書通信費、交通費、宿泊費等 | |
| 研修費 | 会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、文書通信費、交通費、 |
|
| 広報広聴費 | 報告書、広報紙・資料等の印刷費、会場費、 ホームページの作成費及び管理費、茶菓子料、交通費等 | |
| 要請・陳情活動費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 | |
| 会議費 | 会場費、講師謝礼、出席者負担金・会費、資料印刷費、 文書通信費、交通費、宿泊費、食糧費、茶菓子料等 | |
| 資料作成費 | 印刷製本費、翻訳料等 | |
| 資料購入費 | 図書、雑誌、新聞及び資料の購入費、有料データベースの利用料等 | |
| 通信運搬費 | 傭車料、電話代、FAX代、切手・はがき代等 | |
| 備品消耗品費 | 机、椅子、コピー機、パソコン、事務用品、ガソリン代等 | |
| 人件費 | 給料、賞与、各種手当、各種保険等 | |
| 事務所費 | 賃借料、維持管理費、公租公課、保険料、光熱水費等 | |
(2)按分の考え方
調査研究活動等に係る支出とそれ以外の活動に係る支出が一つの支出に混在する場合、それら活動の主体である会派及び議員が、自律的に、政務活動費から支出する割合を判断します。具体的には、「指針」において、次のように定めています。
| ・ 適切な理由に基づき活動全体に占める調査研究活動等の割合を求め得る場合は、その割合により按分します。 ・ 活動全体に占める調査研究活動等の割合を求め難い場合は、「指針」に定める割合を上限として按分します。 |
(3)親族等への支出の考え方
「指針」において、議員の親族等に政務活動費を支出する場合については、特に、次のように定めています。
| ・ 親族等に対する支出については、費目にかかわらず、口座への振込みにより行わなければなりません。 ・ 自宅(賃借するものを含む。)又は議員若しくは議員と生計を一にする者が所有する物件に対する事務所賃借料の支出は認められません。 ・ その他、社会通念上疑義を生じることのないようにしなければなりません。 |
(4)支出が認められないもの
「指針」において、政務活動費からの支出が認められない項目を明確にしています。
| 私的活動に属する経費 |
| 党務等の政党本来の活動に属する経費 |
| 後援会活動又は選挙活動のための経費 |
| 交際費的な経費 |
| 調査研究活動等との一体性が認められない食糧費 |
| 事務所の用に供する土地及び建物の購入経費、自動車の購入経費及び維持管理経費並びに携帯電話の購入経費 |
| 自宅(賃借するものを含む。)又は議員若しくは議員と生計を一にする者が所有する物件に対する事務所賃借料 |
| 議員と生計を一にする者を補助職員として雇用する経費(令和4年度交付分から適用) |
7 政務活動費の執行状況
令和6年度交付分単位:千円(千円未満四捨五入)
| 区分 | 会派分合計 | 議員分合計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 104,720 | 320,800 | 425,520 | |
| 支出額 | 90,769 | 231,826 | 322,595 | |
| 使途項目別内訳 | 調査研究費 | 7,576 | 2,617 | 10,193 |
| 研修費 | 359 | 1,352 | 1,710 | |
| 広報広聴費 | 27,581 | 81,108 | 108,689 | |
| 要請・陳情活動費 | 900 | 28 | 928 | |
| 会議費 | 700 | 141 | 841 | |
| 資料作成費 | 2,435 | 8 | 2,443 | |
| 資料購入費 | 3,147 | 4,749 | 7,897 | |
| 通信運搬費 | 629 | 10,697 | 11,326 | |
| 備品消耗品費 | 4,790 | 9,091 | 13,881 | |
| 人件費 | 42,563 | 78,066 | 120,719 | |
| 事務所費 | 0 | 43,969 | 43,969 | |
| 残額 | 13,951 | 88,974 | 102,925 | |
※ 項目ごとに千円未満四捨五入を行っているため、「会派分合計」と「議員分合計」を足した額と「合計」の額が一致しない箇所があります。
8 収支報告書及び領収書等の提出
政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、翌年度の4月(※1)に使途項目ごとの支出額等を記載した収支報告書に領収書等の写しを添えて、議長に提出しなければなりません(※2)。提出された収支報告書及び領収書等は5年間保存します。
※1 会派が解散し、又は議員が議員としての身分を失ったときは、その翌日から30日以内
※2 その他、出張や研修に関する資料などを任意で提出される場合があります。
9 収支報告書及び領収書等の閲覧・インターネット公開
| 閲覧 | 収支報告書等の写しは、個人情報等を除き、提出期限の約3箇月後から、市会図書・情報室で閲覧することができます。 | |||
| インターネット公開 | 閲覧に供している全ての書類をインターネットで御覧いただけます。公開期間は、1年間です。 | |||