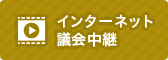令和7年定例会(5月市会)
最終更新日:令和7年6月6日
意見書・決議
地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
消費者被害を防ぐためには、相談体制の確保や消費者教育や啓発など、地方消費者行政の充実・強化が図られなければならないが、国が措置し、地方消費者行政の下支えとなってきた地方消費者行政強化交付金(推進事業)は、令和7年度末には多くの地方公共団体で活用期間が終わるため、交付金を活用して実施してきた相談体制の維持や、啓発・消費者教育に係る事業の継続が困難となるなど、地方消費者行政の後退・縮小が懸念される。
京都市においては、社会における高齢化・デジタル化の進行を受け、65歳以上の高齢者からの相談件数が全体の約3割を占めている。消費者被害が多様化・複雑化する中、消費者への啓発・教育に加え、高齢者や障害のある方等、配慮が必要な消費者への見守りは、喫緊の課題となっている。
また、被害の防止・救済の根幹である消費生活相談においては、相談員の高齢化等による担い手不足が深刻な問題となっている。相談員の担い手を確保し、安定的に業務を継続できるよう雇用形態や処遇等の改善が求められており、国の主導により速やかな制度設計と予算措置を行うことが必要である。
さらに、消費生活相談のデジタル化に向け、国は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に代わる新たなシステムの整備を予定しているが、端末のリース費用や、セキュリティ対策の継続的な更新費用などは、地方公共団体の負担とされており、これらの経常的費用も国の責任で措置すべきである。
よって国におかれては、下記の措置を行うよう強く要望する。
記
1 地方公共団体の財政事情によることなく、地方消費者行政を安定的に推進するための恒久的な財源を措置すること。
2 消費生活相談員の安定的な確保と処遇改善に係る制度設計に必要な予算措置を講じること。
3 国が進める消費生活相談デジタル化に係る予算を国の責任で措置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官
国民健康保険制度に係る財政支援の拡充等を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
国民健康保険制度は、「国民皆保険」の根幹を担う重要な医療保険制度であるが、他の医療保険と比べ被保険者に高齢者が多いことから医療費水準が高く、また、中・低所得者の加入割合も高いなどの構造的な問題を抱えており、その財政基盤は極めてぜい弱である。
加えて、高齢化の進展や医療の高度化等による一人当たりの医療費の増加、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や被用者保険の適用拡大による被保険者数の減少、後期高齢者支援金の増額等に伴う保険料負担の増加が、昨今の物価高騰と相まって、被保険者の負担感は更に増大している。また、令和8年度からは少子化対策の財源に充てられる「子ども・子育て支援金」が保険料に上乗せされることになっている。
平成30年度の国民健康保険制度改革により、都道府県単位での運営、国による財政支援の拡充等、財政基盤の安定化に向けた措置が講じられた。このような中、京都市国保では、平成20年度の1人当たり医療費と保険料をそれぞれ1とした場合に、令和5年度の1人当たり医療費が1.45倍に上がっているところ、一般会計からの繰入金等により、1人当たり保険料は1.03倍に抑えてきた。その結果、京都市国保の令和6年度の1人当たり保険料は、政令市20市や府内15市の中で最も低い金額となっているが、一方で収支不足の問題が深刻化してきた。
今後においても、更なる被用者保険の適用拡大により被保険者数の減少傾向に拍車が掛かることが懸念される。
よって国におかれては、医療保険制度の一本化も含めた医療保険制度の抜本的改革に向けた議論を進めるよう要望するとともに、改革の実現までの間、国庫負担の拡充など、国民健康保険制度への財政基盤のより一層の強化を早急に実施することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
米国の関税措置に対応した中小企業等支援策の拡充を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
米国の関税措置に関し、将来の不確実性が増しており、先般、京都商工会議所が実施した京都企業への緊急影響調査によると、「マイナスの影響を受ける」と回答した企業が約6割を超えるなど、今後、国内への景気下押し圧力のみならず、世界的な景気後退につながるのではないかとの不安の声が寄せられている。
特に、我が国の基幹産業であり裾野の広い自動車関連企業をはじめとする多くの事業者の設備投資への判断や賃上げへの深刻な影響が懸念されており、早急な解決策が求められている。
また、その影響を最も強く受ける中小企業や小規模事業者を守り支えることが、今後の日本経済の成長には不可欠であり、そのためには、中小企業・小規模事業者の生産性向上や価格転嫁等の取引条件の改善等の取組を全力で進め、物価に負けない賃上げと最低賃金の引上げの加速、地域間格差の是正を図ることが重要である。
よって国におかれては、下記のとおり、米国の関税措置に対し、特に日本の企業の9割以上を占める中小企業等を対象とした、具体的かつ手厚い施策を講じることを強く要望する。
記
1 日々状況が変化する中、特に不安が募る中小企業事業者等の声に耳を傾け、丁寧な対応を行うこと。また、各省庁の地方支部や関連団体に特別相談窓口等の体制を整え、不安の払拭に努めること。
2 日本政策金融公庫のセーフティネット貸付について、窓口での積極的な制度の提案やオンライン手続の周知・広報等、事業者の側に立った手厚い対策を講じること。加えて、米国の関税措置による、直接的、間接的な事業者への影響を踏まえてセーフティネット保証制度の適用等の資金繰り支援に万全を期すこと。
3 各省庁・政府関係機関での特設サイトの設置等、政府として可能な限り速やかに、正確で最新の情報を国民や事業者に分かりやすく発信すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、経済再生担当大臣、賃金向上担当大臣、中小企業庁長官
米価の抑制及び米の安定供給を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
昨年来、スーパー等での米の販売価格は昨年の2倍以上に達するなど、現下の精米販売価格は異常な値動きを見せており、家計を圧迫している。
そのような状況の中、政府は、米価高騰の抑制や流通の目詰まりを解消するため備蓄米の活用を決定して競争入札を実施してきたところであり、5月下旬からは随意契約に変更し小売業者等に売り渡すなど、累次にわたり対応している。
これら備蓄米の流通拡大に伴って、銘柄米も含めた米全体の店頭価格が落ち着いて、消費者の選択肢を増やしていくことが重要である。一方、京都市内には、耕作条件が厳しい中山間地域や規模拡大が難しい水田が多く、米農家からは、米価の上昇は米農家の収入増加につながるものの、高騰が続くと消費者の米離れが進むのではないかと懸念され、また、生産コストも上昇しているため、安定した経営を続けていくことに対して不安の声がある。
よって国におかれては、米価格高騰を緊急事態として捉え、直面する課題に様々な手段を講じながら、消費者にとって安定的な価格を早期に実現するとともに、生産者を支援するためにも、下記のとおり、米の安定供給に向けた抜本的な対策を講じるよう強く要望する。
記
1 備蓄米の活用や流通の円滑化については、国民のニーズに応える価格と供給量にスピード感を持って対応し、消費現場にその効果が一日も早く表れるよう推進すること。
2 今後の米の生産・販売の推進に向けた見直しについては、生産者が意欲を持って営農を続けられるよう支援を行うこと。また、各産地が全国の需要に応じた生産量を確保できるよう、取組計画書や営農計画書等の機動的な変更を可能とするとともに、産地との密な意見交換やきめ細やかな情報提供を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣
コメの価格高騰対策と安定供給に向けた農政改革を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
京都市会では、令和6年度5月市会において、「コメの供給不足の懸念に対して適切な対応を求める意見書」を賛成多数で可決し、コメの供給不足の懸念から国に備蓄米の放出等の対策を求めていた。
しかしながら、令和6年8月には大規模災害の懸念を引き金に、「令和の米騒動」と呼称される事態に陥り、その後、新米が流通しても米価の高騰は止まることなく、市民・事業者、地域経済に多大な影響を及ぼしている。本年に入り、ようやく備蓄米の放出を決断したものの、価格高騰の解決には程遠く、現在鋭意取組が行われている。意見書が提出された6月時点又はそれ以前から計画的に対応することで、ここまで大きな混乱は避けられたのではないかと考えると極めて残念である。
また、価格高騰対策だけでは根本的な課題解決には至らない。これまでの減反政策を含む需給調整による営農継続には限界がきているという危機感の下、農政改革を行うべきである。
よって国におかれては、コメの安定供給に向けて種々の改革を行うべく、下記のことを検討し、及び実施するよう求める。
記
1 流通状況の適切な把握と取引の透明化に取り組み、国民に情報を公開するとともに、備蓄米の運用を柔軟に見直すこと。
2 持続可能な営農に向け、農業者の収入拡大への取組を積極的に検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣
事前復興まちづくり計画の策定支援を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
首都直下地震、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震やそれに伴う津波被害、近年激甚化、頻発化する豪雨災害などの大規模災害への備えが、ますます重要になってきている。
大規模な災害が発生すると、市街地をはじめインフラが壊滅的な被害を受ける。被災市町村は、復興まちづくり事業に取り組むことになるが、市街地等の基盤整備は、産業や住宅、教育等の分野の基盤として他分野の復興まちづくり事業に先立って実施しなければならない。そのためにも、早期の復興まちづくり計画の策定、事業着手、事業完了が求められる。
このため、事前に、人口減少や、少子高齢化社会を考え、復興後に想定される居住人口や産業の規模に対し、適切な規模での復興まちづくりの目標や実施方針を検討しておくことは、被災後に復興まちづくり方針・計画を早期に策定し、適切な規模で被災地を復興し、よりよい復興を実現するために重要な取組である。
また、大規模な災害が発生した際には、大規模災害からの復興に関する法律に基づき、国は特別の必要があると認められるときは復興の基本方針を定めるとともに、都道府県においても復興方針を定めることができるとなっており、これらに基づき復興計画を策定することができるとされている中、京都市においても事前復興に関する取組を進めているところではあるが、不断の取組を進めていくべきである。
国土交通省では、地方公共団体による復興まちづくりをイメージした目標像の検討や、その実施方針の検討等を通じた事前復興まちづくり計画の事前の策定に焦点を当てた「事前復興まちづくり計画検討のためのガイドライン」を策定した。
一方、地方公共団体の復興事前準備の取組状況は、令和6年7月末時点で着手率が約67%となり、取組は一定程度定着してきていると考えられる。
災後に迅速な復興まちづくりを行うには、平時から災害が発生した際のことを想定し、事前に体制と手順の検討、建物や土地利用状況などの必要なデータの整理、復興まちづくりの目標の検討などを行う復興事前準備に取り組むことが重要である。
よって国におかれては、事前復興まちづくり計画策定に対して防災・安全交付金による支援や、事前復興まちづくり計画の策定を検討し、実施する自治体に対する技術的助言などの支援を強化されるよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、国土強靭化担当大臣
観光課題及び観光客受入環境整備に係る意見書
(令和7年6月6日提出)
現在、国際観光旅客税(出国税)の使途は法により規定され、出入国手続の高度化、世界水準の受入環境整備、地域固有の文化・自然等を活用した新たな観光コンテンツの拡充などに活用されている。
京都市においては、コロナ禍後、観光需要が急速に回復し、多くの観光地がにぎわいを取り戻している一方で、地域住民の生活への影響も生じている中、これまでも、国においては、 「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」に基づく取組を進めてきた。
今般、第217回国会参議院予算委員会において、石破総理から出国税の見直しについて検討するとの発言があり、今後議論が深まっていくものと認識している。
よって国におかれては、自治体における観光課題対策等の取組の更なる推進に向けて、下記のことを検討するよう求める。
記
1 国際観光旅客税の使途については、観光客の受入れと住民生活の質の確保を両立し、持続可能な観光地域づくりに向け、事業を実施する自治体が柔軟に活用できるよう、自治体の意見をしっかりと取り入れた制度とすること。
2 速やかに観光客数等の観光実態を把握する統計を整備するとともに、将来的な当該税制度の見直しも含めて、自治体が実施する観光課題対策や観光客受入環境整備事業等について、十分な財政支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(地方創生)、国税庁長官、観光庁長官
国際観光旅客税収の地方自治体への配分を求める意見書
(令和7年6月6日提出)
日本からの出国者に対し1人1,000円が課税されている「国際観光旅客税」(出国税)について、財務省は令和7年6月2日に、令和6年度の税収が集計期間を1か月残した段階で481億円に達し、過去最高の税収となる見込みであると公表した。
現在行われている第217回通常国会において、石破総理が国際観光旅客税の引上げの検討について答弁するなど、政府において具体的な引上額や対象範囲について検討が進められている。
この税収の使途については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等」に基づき、多言語対応の強化や戦略的な訪日プロモーションなど、国の事業に全額充当されている。
しかしながら、多くの訪日観光客を受け入れる環境の整備や、観光客にとっての魅力ある文化や街並みの整備を実際に行っているのは市町村であり、とりわけ多くの訪日観光客が訪れる京都市においても、オーバーツーリズムや観光課題の解決に、市の財源の多くを投じている。
よって国におかれては、観光客数や宿泊者数などの客観的指標に基づき、国際観光旅客税収の一部を地方自治体に直接配分することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(地方創生)、国税庁長官、観光庁長官
沖縄戦の歴史に真摯に向き合うことを求める決議
(令和7年6月6日提出)
令和7年5月3日の憲法記念日に那覇市で開催されたシンポジウムにおいて、西田昌司参議院議員は、沖縄県のひめゆりの塔の展示をめぐり、展示の説明が「日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆり(学徒)隊が死に、米国が入ってきて、沖縄が解放されたという文脈で書いている」として「歴史の書換え」などと発言をされた。
この発言については、沖縄県議会が抗議の決議を行うなど、多くの抗議の声が上がり、また、石破総理も歴史が書き換えられたなどという発言については「認識を異にする」と衆議院予算委員会で答弁しており、沖縄県の玉城知事と面会した際、「ひめゆりの塔」の説明を巡る西田議員の発言に「大変申し訳ない発言で、自民党総裁として深くおわびする」と陳謝している。西田議員の発言や見解は、沖縄県民の心を深く傷つけるものと言わざるを得ない。
これまでから日本国政府は、談話や国会答弁などで、先の大戦において、沖縄は国内最大の地上戦を経験し、多くの方々が犠牲となり、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたこと、何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実があること、悲惨な経験を風化させることなく、次の世代に継承することが重要であることなどを、公式な立場として表明してきた。
また、沖縄戦においては京都出身者の多くも犠牲となり、戦後、京都の多くの議員の先人たちが党派を超え沖縄と京都とを結ぶ文化と友好との絆を深めてきた。
京都市会として、京都選出の議員がこのような発言をしたことに強い遺憾の意を表明するとともに、沖縄県民の心情に寄り添い、沖縄戦の歴史に真摯に向き合うことを求めるものである。
以上、決議する。
北陸新幹線の京都市内大深度トンネルルートへの反対決議
(令和7年6月6日提出)
現在、北陸新幹線の敦賀から大阪への延伸に関して、いわゆる小浜ルートとして敦賀から小浜を経由し京都市内の大深度地下にトンネルを建設する計画について、環境アセスメントが進められている。
この計画については、市民はもちろん様々な団体や専門家から、問題があり撤回すべきだとの強い意見が本市へも届けられているところである。
地下水への影響、ヒ素を含む可能性のある大量の残土の処理、工事期間中の渋滞、地元負担の非提示、住民への情報非開示、歴史的・文化的建造物への影響、根本的なB/Cつまり採算性などについて問題のある状況で、現在の計画をこのまま進めることは、京都市の未来に向けて重大な問題を招くと考えるため、京都市内大深度トンネルルートへの反対を表明する。
以上、決議する。
北陸新幹線延伸計画に係る国等の適切な対応を求める決議
(令和7年6月6日提出)
北陸新幹線延伸計画については、現在、京都市内を通る2つのルート案が国から示され、地元関係者等の懸念や不安を払拭するため最善を尽くすという方針の下、昨年度末には、国や事業主体である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が京都府内の自治体向けに説明会を開催したところである。
京都市内を通る場合、地下水への影響や建設発生土への対応、工事車両による交通渋滞、京都市財政への影響に加え、文化・歴史的建造物等への影響などの懸念があり、これまでから国や鉄道・運輸機構には地元の意見を伝えたところである。
北陸新幹線については、国策としての意義は認めるものの、市民や事業者の体感的な納得を得られることが不可欠である。
よって国や事業主体である鉄道・運輸機構においては、早期の事業推進に当たり、地域の声をしっかりと受け止め、十分な科学的根拠に基づき慎重かつ丁寧な説明を行うなど、適切に対応することを求める。
以上、決議する。