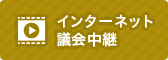令和6年定例会(令和7年2月市会)
最終更新日:令和7年3月25日
意見書・決議
重度障害者の住まいの場の整備に係る財政支援の強化を求める意見書
(令和7年3月25日提出)
障害者の自立支援の観点から、入所施設から地域生活への移行については、適切に意思決定支援を行いつつ地域生活を希望する方が暮らしを継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要がある。本市においては障害者向けのグループホームや短期入所施設等の整備が現状十分とはいえず、家族の負担が大きい状況が続いている。
今後、障害者の生活を支えてきた親が高齢等により亡くなった後も住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域における住まいの場を確保することが喫緊の課題となっている。このような中、特に支援が必要な重度障害者が安心して生活をすることができるグループホームの整備を進めることは、入所施設や在宅で暮らす重度障害者の住まいの場の選択肢の一つとして、また、入所等から地域生活への移行や、支援が必要な重度障害者の在宅からの入所を進めるうえで重要である。
また、強度行動障害や重複障害といった支援の困難さを抱える方や、高齢により在宅支援が困難な状況にある家族の声を丁寧に聴き、障害者やその家族にとって必要な福祉施設を整備していくことも重要である。
さらに、既存のグループホームや入所施設等は、老朽化が進行している場合もあるため、大規模修繕への対応や、担い手の育成支援も急務である。
よって国におかれては、人的支援はもとより、重度障害者の住まいの場となるグループホームや障害者やその家族にとって必要な福祉施設の整備及び既存の施設の大規模修繕に対する地方自治体への財政支援を強化することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(共生・共助)、共生社会担当大臣
白タク行為への実効性のある対策を求める意見書
(令和7年3月25日提出)
国内外の観光需要は急速に回復し、多くの観光地がにぎわいを取り戻している一方、観光客が集中する一部の地域や時間帯等においては、過度な混雑の発生や、マナー違反の行為等により、地域住民の生活にも影響が生じている。
さらに、訪日外国人旅行者等が多数訪れる京都市内の観光地や主要駅等においては、道路運送法に定める国の許可を得ず、一般のドライバーが自家用車を使って有料で乗客を送迎する違法行為(いわゆる白タク行為)が疑われる車両が、時期や曜日を問わず日常的に見受けられる状況にある。
白タク行為は、タクシー事業者の事業活動を阻害することはもとより、本来タクシーが客待ちできない道路や駅の乗降場等においても行われることで、混雑や、他の車両通行の支障等といった問題を引き起こしている。また、乗客の安全性が担保されていない状況にもなっている。
昨年6月にデジタル行財政改革会議にて決定された「デジタル行財政改革 取りまとめ 2024」において、白タク行為に対しては、違法な仲介行為を停止するよう行政指導をするとともに、広く共犯規定を駆使した取締りを引き続き強化していくとの方針が示されている。
京都市においては、関係機関・団体と連携し、観光地等で白タク行為の違法性や危険性を周知する啓発活動を実施するなどの取組を進めているが、依然として白タクと疑われる車両が後を絶たない状況にある。
よって国におかれては、違法である白タク行為の根絶に向けて、より実効性のある対策を検討し、実施することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)、行政改革担当大臣
性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書
(令和7年3月25日提出)
性犯罪をした者に対して、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されているが、出所後も地域社会において継続することが重要である。
令和5年3月、法務省は、自治体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン~再犯防止プログラムの活用~」を策定し、このガイドラインを踏まえて、性犯罪の再犯防止に都道府県等が主体となって取り組むことが期待されている。
性犯罪をした者の出所後の住所等については、法務省から情報提供を受け都道府県等が把握する仕組みはなく、実際に当事者に対して直接再犯防止の取組を行うことは困難であるため、一部の都道府県では、子どもに対して性犯罪をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、届け出られた情報を基に、カウンセリング等の再犯防止・社会復帰支援を行っている。
こうした条例に基づく届出の仕組みがなくとも各自治体が再犯防止の取組を効果的に進めるためには、国、自治体、関係機関等の連携や性犯罪をした者に係る情報の共有が極めて重要であり、国からのより一層の支援が不可欠である。
よって国におかれては、下記の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も自治体による再犯防止プログラム等を受ける意義について啓発を図ること。
2 再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等を出所する際に、当事者の住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、届け出られた情報を自治体に提供すること。
3 自治体では、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を十分に有していないことから、再犯防止に係る人材の育成について支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、厚生労働大臣
選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書の提出
(令和7年3月25日提出)
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とし、我が国では夫婦同姓制度が採られている。このため、婚姻に際しては、夫又は妻のいずれか一方が必ず姓を改めなければならないところであるが、現実には、夫の姓を選び、妻が姓を改める例が95%近くに上っている。名義変更の負担に加え、仕事上の姓(通称)と戸籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている現実がある。
平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合には、それぞれ結婚前の氏を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申したが、当時は国民の間にも様々な意見があったことから、改正案の国会提出には至らなかった。以降、議論は長年にわたって行われてきた。
その後、最高裁では、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方で、夫婦の姓に関する制度の在り方については、国会で論じられ、判断されるべきであるとされたところである。
そのような中、令和6年6月、日本経済団体連合会は、夫婦別姓を認めない今の制度は、企業にとってもビジネス上のリスクになり得るなどとして、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を早期に行うよう提言した。同年10月には、国連の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓の強制を廃止するよう4度目の勧告を行っている。
法制審議会の答申から30年近くを経た今、世論調査でも様々な意見があり、多様な選択肢を広げるための議論を国民に理解してもらう努力が求められている。
よって国におかれては、選択的夫婦別姓制度の国民理解と制度化に向けて下記の点に取り組むよう強く要望する。
記
1 制度に関する情報発信を積極的に行うこと。
2 家族ごとの戸籍制度を守りつつ、別姓の選択も尊重される制度を設計すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。