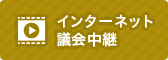令和6年定例会(5月市会)
最終更新日:令和6年6月20日
意見書・決議
手話言語における適切かつ時代に即した表現の在り方の議論と普及を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
本市では、平成28年に「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例(手話言語条例)」を議員提案により全会一致で可決・施行するとともに、手話は言語であり、手話に対する理解の促進に努めることで、手話を必要とする人を含め、全ての人が相互に人格と個性を尊重することができる豊かな共生社会の実現を目指して取り組んできたところである。
その一環として先般、令和6年6月4日に、手話を用いた「手歌」と歌声を奏でるホワイトハンドコーラスNIPPON京都支部の子どもたちの訪問も受け、更なる共生社会の実現を目指す団体の活動を御紹介いただき、日頃の活動の成果として手歌パフォーマンスを御披露いただいた。
その際、手話には、イメージを手の動きで表現する言葉がある中で、「障害者」と表現する場合には、「壊れた」「人」と表現するため、「私たちは壊れた人ではなく「個性のある人」である、と広めたい」との訴える声があった。
この「壊れた人」との表現は、障害の概念が、かつての医学モデルから社会モデルに変化し、社会的障壁を取り除く取組が求められる時代にあって、これから手話を学ぶ人や日本の未来を担う子どもたちに誤解を生じさせかねないと危惧されるものである。
ただし、手話を第一言語とする人たちの参画なしに手話表現の在り方を議論することは適切ではなく、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の精神はしっかりと尊重すべきであり、加えて、手話では、「障害者」という語句をそのまま表現しているにすぎないことから、そもそも「障害者」という語句の在り方を含めて議論する必要もあると思料する。
よって国におかれては、手話を第一言語とする当事者の団体との間で、時代に即した「障害者」という語句及び手話表現の在り方を丁寧に議論し、その在り方や考え、取組を広く国内に普及されることを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、共生社会担当大臣
介護従事者の処遇の改善に資する必要な措置を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
京都市会では、令和5年10月に介護報酬等の物価高騰・賃金上昇への対応を求める意見書を国に提出したところである。
こうしたことも踏まえ、令和6年度の介護報酬改定においては、介護報酬全体として1.59%の増額改定、さらに、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として0.45%を見込み、合計で2.04%相当の増額改定となったことで、介護従事者の賃上げや今般の物価高騰への対応がなされたものである。
一方で、訪問介護については、国が実施する介護事業経営実態調査において、収支差率が全サービス平均を大きく上回っていたことを踏まえて基本報酬が減額改定となったことにより、とりわけ小規模・零細事業所からは、経営が厳しい、あるいは処遇改善加算の算定を得ることが難しい、ベースアップが確実に実行される保証がない、といった声が寄せられている。
こうした中、令和6年6月5日の衆議院厚生労働委員会においては、「介護・障害福祉分野の人材の確保及び定着を促進するとともにサービス提供体制を整備するための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する件」について、全会一致で決議されたところである。
よって国におかれては、介護事業所の経営安定化と、介護サービスを担う優れた人材の確保及び定着をより一層促すため、下記の事項に取り組まれるよう要望する。
記
1 今般の衆議院厚生労働委員会の決議を踏まえ、令和6年度の介護報酬改定の影響について、訪問介護事業所をはじめとする介護事業者等の現場の実態を速やかに調査・検証をすること。
2 その調査・検証の結果、介護従事者の処遇の改善及び経営の安定化に資する対策を早急に検討し、必要があると認めるときは、3年に1度の報酬改定の時期を待たずして速やかに措置を講じること。また、介護報酬の増額改定等を行う場合は、保険料や利用者負担の引上げにつながらないよう全額国庫で賄うなど、必要な措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣
災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
災害発生時における情報の真偽は、多くの人々の命に直結する重要なものである。本年1月に発災した能登半島地震をはじめ、過去の様々な災害においても偽情報・誤情報が、救援・復旧の現場に大きな混乱を招いてきたところである。災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の確立は喫緊の課題であることから、その構築に向けて積極的に支援するとともに、正確な情報を得るための画像認識技術の導入、また、防災の知見を兼ね備えた専門家の活用も重要である。
京都市においては、国の新たな総合防災情報システムを活用し、災害時の情報収集・分析体制の強化が可能となったところである。
よって国におかれては、下記の事項について特段の取組を求める。
記
1 情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の信頼性を担保し、現場からの正確な情報を収集し活用する情報連携環境を整備すること。
2 IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムでの国と地方自治体の災害情報共有体制を整備すると同時に、適切な情報分析と迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治体への配置を支援すること。
3 正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーション等について、国民への普及を強力に推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、国土強靭化担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、気象庁長官
聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の一つといわれており、また難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。
この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で、様々な原因で外耳道が閉鎖している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。
近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。
京都市では、ヒアリングループの設置、字幕表示システム「Cotopat」の導入など、本市施設や各区役所・支所の窓口におけるコミュニケーションの円滑化に向けた環境整備を積極的に進めている。
よって国におかれては、このように、様々な聞こえに課題のある方に適用できる聴覚補助機器等の選択肢が広がった今、我が国の更なる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防とともに、高齢者をはじめ、聞こえに課題のある方の積極的な社会参画を実現するために、下記のとおり聴覚補助機器等の積極的な活用を促進する取組を強く求める。
記
1 高齢者や難聴者等の聞こえに課題のある方が、医師や専門家の助言の下で、自分に合った補聴器をはじめ、最新技術を用いた聴覚補助機器を積極的に活用する環境を整えること。
2 高齢者や難聴者等の聞こえに課題のある方と円滑にコミュニケーションを取れる社会構築を目指し、行政等の公的窓口等に、合理的配慮に関する環境整備の一環として聴覚補助機器等の配備を推進すること。
3 地域の社会福祉協議会や相談支援機関との連携の下、聴覚補助機器等を必要とする人々への情報提供の機会や場の創設等、最適な聴覚補助機器を普及させる社会環境を整えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、共生社会担当大臣
ライドシェア事業に係る法制度については地域の実情や課題を踏まえ、慎重な検討を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
日本版ライドシェアの先行実施自治体として京都府が選定され、本年4月から始まったところであるが、5月末には、斉藤国土交通大臣から「検証に十分な時間を掛けることが必要で、早急に結論を出すべきではない」との考え方が示された。一方で、政府の規制改革会議においては、「来年の通常国会において関連法案の提出を目指すべき」との声も一部あると聞く。
ライドシェアの議論に当たっては、「利用者の安心・安全」、「市民生活や円滑な道路交通の確保」、「バス・鉄道を含む公共交通事業者の経営や運転士、とりわけタクシーのドライバーをはじめとする担い手の雇用」等といった観点について、地域の実情に即した十分な配慮が必要である。
本年4月に創設された「日本版ライドシェア」は、エリアや時期・時間帯等によっては、現況の交通課題への対策として一定の効果を発揮する可能性も考えられる。
一方で、市街地中心部や嵐山、東山等といった地域では、更なる車両集中で、市民生活や道路交通に大きな支障を来すおそれがあり、収益性の高いエリアのみに参入し、地域の足を広く担う公共交通事業者の経営や雇用への悪影響が生じるおそれなど、現実的には多くの問題が発生することも予想される。
現在、交通の空白地域及び時間帯による空白が発生していることも事実であり、これらの課題解決のために、京都市域で試行実施をしている「日本版ライドシェア」や京都府京丹後市などの交通不便地域で導入している道路運送法第78条第2号に基づく、いわゆる「自治体ライドシェア」などで検証を進めているところである。
よって国におかれては、今後これらの検証や議論において、まず何よりもタクシー乗務員の増員に取り組み、地域の実情や課題を十分に踏まえること。特に、「ライドシェア」を導入した諸外国では、制度化後に訴訟提起が相次いでいるという問題点もしっかりと把握し、安易に「ライドシェア」を制度として導入するのではなく、安心・安全面の確保を第一に地域交通課題解決に向けた検討をすることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)、内閣府特命担当大臣(地方創生)
ミャンマー国軍による暴力行為の即時停止と民主的政治体制の早期回復の働き掛けを強く求める意見書
(令和6年6月20日提出)
ミャンマーの国営メディアは、2024年2月10日、男性は18歳から35歳まで、女性は18歳から27歳までに対する徴兵制の導入に向けて「人民兵役法」を施行すると発表した。徴兵の開始は、ミャンマー歴の正月に実施される「水祭り」(4月21日)明けからとされ、毎月5,000名を目標に訓練を開始する方針であることを国軍報道官が伝えた(2月20日、女性は一旦除外すると発表)。これは、劣勢を強いられる軍が、深刻化する兵員不足を補うねらいがあるとされているが、民主派のNUG(国民統一政府)が2月13日に発出した声明での「国民を戦争の最前線に送り「人間の盾」に利用しようとしている」という指摘に見られるように、多くの若者が犠牲になるばかりか、民主主義を希求する国民同士に殺し合いをさせる、卑劣な制度の実施であることは疑う余地もない。
徴兵制を拒否すれば禁固刑の罰則もあり、中立も許さず、絶望した若者たちには反発や動揺が広がり、国外脱出を図る者が続出している。自殺者も出ていると伝えられる。まさに踏み絵を迫る制度である。
我が国では、本年2月1日、クーデター後3年に当たり、外務大臣が、ミャンマー情勢が年々悪化していることを深刻に懸念していると表明し、ミャンマー国軍が空爆などの暴力によって多くの無辜(こ)の市民が日々死傷している状況を強く非難した。また、国際機関のみならずNGОなどともより一層連携し、引き続き、人道支援を積極的に行い、また、ミャンマー軍に対しても、安全で阻害されない人道アクセスを認めるよう強く求め、ミャンマーの人々の声に耳を傾け、様々な関係者と対話し、ASEANとの連携をより強化することによって、事態打開に向けて取り組む旨の発表をした。さらに、3月8日には、外務省は、全国で約230万人の市民が避難生活を強いられている危機を受け、様々な人道支援策を追加することを表明した。
よって国におかれては、「平和都市宣言」、「世界文化自由都市宣言」の下、ミャンマーの若者たちの未来を守るため、下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 WPS外交をしなやかに具現化するべく、日本外交の影響力を最大限推進し、「ミャンマー問題」は忘れてはならない紛争であることを世界に発信し、国連やASEANをはじめとした国際社会と連携して、クーデター直後に開催されたASEAN首脳級会議において発出された「5項目コンセンサス」を速やかに履行するよう繰り返し求め続けること。
2 今この瞬間も続く、ミャンマー軍による空爆、民間人に対する残虐行為を即時停止し、及び恣意的な死刑執行を一切行わないよう求め、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問をはじめとする不当に拘束された人々を即時解放し、対話による平和的解決のためにも、民主的な政治体制の早期回復・実現を粘り強く求めること。
3 現在、日本全国に在留する8万6,000人余りのミャンマー人が、安心して働き、学び、暮らしていけるよう対策を講じているが、依然予断を許さないミャンマー国内の情勢に照らし、緊急避難措置の継続等、今後も必要な対策を検討し、及び実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、出入国在留管理庁長官
コメの供給不足の懸念に対して適切な対応を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
2023年の猛暑による不作やカメムシの大量発生、外食需要の高まり等を背景に、コメの供給不足を心配する声が流通現場で広まりつつあり、コメの価格高騰も顕著になってきている。
既に、SNSや報道番組で取り上げられているほか、一部スーパーではコメの大量購入を控えるよう張紙がされる等、より多くの消費者に不安感が広まるのも時間の問題である。また、食料品の価格高騰が続く中、主食であるコメの不足や価格高騰は、国民生活に大きな不安と混乱を招くことは間違いない。
「平成のコメ騒動」とは不作の状況や民間在庫の量が大きく異なっており、政府は、深刻な状況ではないという説明を行っているが、インターネットやSNSの普及によるフェイクニュースを含む情報源の曖昧な情報が拡散される危険性、転売目的の買占め、インバウンドによるコメ需要の増加等、平成とは時代背景が違う中、コメ不足に対する不安が広まり、混乱が生じることの懸念は払拭できない。
よって国におかれては、コメの供給不足の懸念に対処すべく、下記のことを検討・実施するよう求める。
記
1 コメ農家の経営に配慮しつつ、コメの不足や価格高騰が国民生活へ与える影響に鑑み、備蓄米の放出を検討すること。
2 フェイクニュース等の拡散による混乱を避けるため、正しい情報発信を積極的に行うこと。
3 国において、コメの需給管理を責任を持って行い、米価の安定的保障をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣
下水道の維持管理・更新におけるウォーターPPP導入に向けての丁寧な対応を求める意見書
(令和6年6月20日提出)
公共インフラの適切な維持管理や更新は、地域住民の日常生活の安全と安心のために大変に重要な課題である。地方公共団体が整備や維持管理を進めてきた下水道は、今後、大量に更新時期を迎えることが予想され、京都市においても同様である。
この地方公共団体の下水道事業においては、施設の老朽化に加えて、人口減少による使用料収入の大幅な減少、職員数の減少による管理や運営状況の悪化に対し、広域化やDXをはじめとする効果的・効率的な取組が求められている。
国は、更新時期を迎える公共インフラの適切な維持管理や更新のために、PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年改定版)を策定し、下水道において、官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式(ウォーターPPP)の導入を推進することとした。
さらに、国は、社会資本整備総合交付金等の交付要件について、「汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和9年度以降に要件化する」とした。
このPPP/PFI手法の導入は進みつつあるが、仕組みが複雑で検討も多岐にわたる。本市ではこれまでDBO、PFIなどの様々な官民連携手法を取り入れてきたが、今後更なる効率的な維持管理更新のため、PPPに関しても研究・検討を進めていくところである。
よって国におかれては、地方公共団体が民間との連携の下で、主体的に安定的かつ持続的に下水道施設を機能させることができるよう、ウォーターPPPの導入について、下記の特段の配慮を求める。
記
1 地方公共団体への導入支援において、相談窓口の開設や、専門家の派遣等の伴走型の支援体制を整えること。
2 社会資本整備総合交付金の交付における「汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであることを令和9年度以降に要件化する」との国の方針について、地方公共団体の取組状況に応じて弾力的な対応を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。