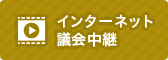摘録
最終更新日:令和6年6月27日
令和6年6月20日
報告案件
<1.5月市会の議案審議結果>
それでは、本日終了しました、令和6年京都市会定例会5月市会の議案審議結果について報告いたします。5月市会につきましては、5月31日から6月20日までの21日間の審議期間で開催いたしました。
今市会では、松井市長の公約に盛り込まれた政策的な事業等を計上する「第二次編成」予算を中心に審議しました。
令和6年3月市会において議決された「第一次編成」予算に続き、収支均衡予算となりました。
「第二次編成」予算は、「第一次編成」予算と合わせ、京都の未来へとつながる第一歩となる予算です。
市民の皆様がこれからも安心して暮らしていただける京都であり続けるよう、市会といたしましても、市の取組が京都市の課題を解決していくことができるものなのか等について、活発な議論を行いました。
私個人としては、本会議や委員会では、特に、子育て・教育環境の充実や、観光課題への対策、地域公共交通の維持・確保についての議論が活発であったように感じております。
皆さんが安心して住み続けられる、安心して子育てもできる京都となるよう、これからも議論を継続し、市会の役割を果たしてまいりたいと思います。
それでは、お手元の資料、「5月市会審議結果総括表」をご覧ください。
市長から提出されました議案は、「令和6年度京都市一般会計補正予算」など、計28件ございました。
市会では、本会議で市長、副市長から提案説明を聴取し、9名の議員による代表質疑を行った後に、予算特別委員会における局別質疑や市長、副市長に対する総括質疑、さらには常任委員会において活発な議論を行ったうえで、28件を原案のとおり可決しました。
また、意見書については、8件可決し、「手話言語における適切かつ時代に即した表現の在り方の議論と普及を求める意見書」などを国に提出することとしました。
その他、請願については、5件を不採択といたしました。
「5月市会の議案審議結果」については、以上でございます。
<2.京都市ケアラー支援条例(仮称)の制定に向けた取組>
次に、京都市ケアラー支援条例(仮称)の制定に向けた取組についてでございます。近年、ケアラーに対する支援の必要性について社会的認識が高まる中、全国の自治体においてもケアラー支援に関する条例制定の動きが進んできております。
併せて、これまでから京都市会においても、各会派から、執行機関に対して条例について質疑がなされたり、関係団体の活動に参加されているなど、条例の制定に向けた市会全体の熱意は高い状況にありました。
これらの状況を踏まえ、京都市会では、ケアラー支援に関する条例について、議会一体となって取り組むこととし、各会派の代表者で構成するプロジェクトチームを設置したところであります。
5月31日には、プロジェクトチームの発足式を行うとともに、「ケアラー支援条例をつくろう!ネットワーク京都」から要望書を受領いたしました。また、受領式の後、第1回のプロジェクトチーム会議を開催し、同団体からの意見聴取及び懇談を行いました。
今後、プロジェクトチームにおいて条例案の検討を進め、当事者や関係団体等からご意見を伺い、また、パブリックコメントを実施したうえで、9月市会において、市会議員全員の共同提案により、全会一致での可決を目指しております。
ケアラーが孤立することなく、安心して暮らすことのできる社会となるよう、引き続き、市会として取組を続けてまいります。
<3.「ホワイトハンドコーラスNIPPON」の表敬訪問>
最後に、「ホワイトハンドコーラスNIPPON」の表敬訪問についてでございます。京都市会では、平成28年に議員提案によって「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」(手話言語条例)を全会一致により制定しており、手話への理解促進・普及に取り組んできたところです。
6月4日に、ホワイトハンドコーラスNIPPON京都支部の皆様が、更なる共生社会の実現を目指し、同団体の活動を紹介するため、京都市会を表敬訪問されました。
表敬訪問では、日頃の活動の成果として、市会本会議場においてパフォーマンスを御披露いただきました。手話を用いたパフォーマンスはとても表現豊かで、皆さんが全身で音楽を楽しまれている姿に感動いたしました。
パフォーマンスを御披露いただいた後は、皆様と、私や副議長、市会運営委員会の理事で懇談を行いました。
出席議員が手話によりあいさつをさせていただいたほか、ホワイトハンドコーラスNIPPONの日々の活動内容や活動に懸ける思いを伺いました。
このたびの表敬訪問を通じ、「手話で歌う」という表現手法に感銘を受けるとともに、手話を用いることで障がいのある方に新しい世界がひらけていく、手話の可能性を改めて感じました。
京都市会といたしましても、引き続き、手話の普及に取り組んでまいりますとともに、今回の貴重な機会を、さらなる共生社会実現に向け、生かしてまいります。
私からの報告は、以上です。
質疑応答
<発表案件に関する質疑>
記者
ケアラー支援条例について、二点改めてお伺いしたいのですが、議員提案条例として制定を目指すにあたり、議長としての所感を一点お伺いしたいのと、二点目は今後どのように取り組んでいかれるのか、具体的によろしくお願いします。
議長
ケアラーについては、介護離職が問題になったり、大きく社会問題となっているところですが、ヤングケアラーにおいては、心身、また、学業や心労など、様々な影響が生じるなど、その支援の必要性について、社会的に意識が高まっており、重要な課題と考えております。
京都をケアラーの方々にとって温かな場所としていくため、その後押しとなる条例の制定を議会として、目指してまいりたいと思います。
プロジェクトチームにおいては、当事者や市民の皆様の声に真摯に向き合い、丁寧に議論を進めていただきたいと思っております。
今後の取組について、5月31日に設置した各会派での代表者で構成するプロジェクトチームにおいて、今後条例の制定に向けた検討をしていただくことになると思います。現在は、関係団体や当事者の皆様から意見聴取を行っているところです。
今後の予定としてはパブリックコメント等を行い、市会議員全員の共同提案により、9月市会において全会一致で可決を目指してまいりますが、取組の詳細については、プロジェクトチームで協議され決まっていくことでございます。
プロジェクトチームにおける取組状況は適宜発信し、また皆様にお知らせさせていただきたいと思います。
記者
本日、閉会の時にミャンマーの内政の意見書をめぐり、自民党と公明党の議員が退場されましたが、理由をお伺いします。
議長
なかなか答えづらいのですが、この件につきましては、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるという、地方自治法第99条の趣旨に馴染まないことが理由とお聞きしております。
また、内容がミャンマーという外国の内政に関する内容であることから、地方議会である京都市会が賛成、あるいは、反対の意向を示せるものではないと思います。
また、他の会派にもそのようにお伝えしましたが、理解いただけず、やむを得ず退席となったとお聞きしております。
記者
ケアラー支援条例の取組のことで伺います。
関係団体や当事者からの意見聴取は、本来であれば本日までであったと思いますが、募集期間を延長されると事務局から聞きました。延長された理由は、どのようなものがあるのか、伺えますか。
議長
その件については、事務局に聞いていただけますか。
記者
ケアラー支援条例で、全会一致での可決を目指されるということで、ただ、会派もそれぞれ考えがあって、会派がそれぞれ別だということも、当然いろんな政治課題があって、いろんな考え方があるという中で全会一致を目指すとなると、その意見調整などが大変になると思うのですが、全会一致するためにはどのようなところがポイントになり、どのようなことが全会一致に必要か、お考えを伺えますか。
議長
特定の事柄ではなく、しっかりと社会全体で支援していくという点において、どこかが賛成して、どこかがずれるということではなく、しっかり全会一致するというのが、一番、これを進めるのにはふさわしいと思います。
時間をかけて、議論を深めていく、協議していく、また、関係団体の皆様に、どこがというところもしっかりお聞きしたうえで取り組んでいくということに尽きると思います。
記者
先ほどのミャンマーの件で、内政に馴染まないとお答えいただいたと思いますが、例えば、ウクライナの侵攻に対しての意見書が提出されていたり、他のこともありますが、ミャンマーだけが特別内政に馴染まないという、なぜミャンマーだけそのようなことになるのでしょうか。
議長
ミャンマーだけではなく、いろんな事柄について、内政干渉しにくいものについては、意見書を出すということに馴染まないのではないかと思います。
記者
内政干渉しにくいものについてはということですが、ウクライナ侵攻に対して、今検索したら出てきたのですが、姉妹都市キエフ市をはじめとする各都市へのロシアによる軍事侵攻に抗議する決議は、どのように理解すればよいのでしょうか。
議長
平和に関することについては、難しいですね。
副議長
ウクライナの時は、基本的にはロシアが侵攻したということで、平和をということなのですが、今回の意見書は、例えば徴兵制のことなど、具体的な事項にかなり踏み込んでいると思います。
それが一点と、もう一点は、そのことについて、政府もすでに、態度を明確に外務大臣の談話などで発表しておりますので、そういう意味では、議長と私たちこの退席した会派ですが、会派の議論の中でこの退席したというのは、賛成や反対といった判断までは付けにくいということです。
記者
活発な議論があったと、議長から先ほどお話があったのですが、具体的に活発な議論があって印象に残っていることは、具体的にどういったことでしょうか。
議長
人口減少化社会の中では、少しでもそれを食い止めるような事柄や、どのように経済を活性化させていくか、経済だけではなく、地域の活性化も含めて、そういう活発な議論があったと思っています。
記者
もちろんそういうことはされてると思うのですが、具体的に、こういう補正予算のこういう事業の中のやりとりで、印象に残った具体的なエピソードや、やりとりを伺いたいと思います。
議長
全体を通して申しました。
記者
個別事案で、印象に残っていることは特にないのでしょうか。
議長
全体で見ておりますので。
記者
全体を見ているとのことですが、一つ一つのやりとりはもちろんお聞きになっていますよね。
その中で、今回松井市長が新しく市長になられて、第二次編成の中で、これはやりとりとしては活発だなというものはありますか。
議長
若い子育て世代の方が、例えば家を買う際の支援ですね。
記者
家というのは中古住宅でしょうか。
議長
そうです。購入する際にお金を支援するという事業があったと思います。
記者
それが印象に残っていらっしゃるということですね。どういうところが印象に残っていますか。
議長
若い人が、経済的に苦しい状況にあっても、中古住宅を購入することによって支援を受けられる、また、何に使ってもいいのであれば、非常にありがたい支援になる、お金の流れになると思って聞いておりました。
記者
200万円の補助はお金に困っているというよりかは、京都市内の特にマンションが高いなどで、なかなかということもあると思いますが、そういったことも含めてでしょうか。
議長
もちろん、そういうことも含めてです。